目次
- 1. 靴下は全て同じものにする
- 2. 洗濯は“干さない”運用にする
- 3. 畳まない服の収納に切り替える
- 4. 掃除は“床に物を置かない”で8割解決
- 5. 収納は“備え付けのみ”と決める
- 6. 作り置きは“味付けなし”で応用する
- 7. 家電やサービスは“判断基準”を明確にして導入
- おわりに:「頑張らない家事」が暮らしを整える
これは「働きながら、ひとりで家事を回す」人向けの記事です。
家事を完璧にやるより、“生活を整える最低限の工夫”で、心の余白を作ることを目指します。
はじめに:家事は“こだわりすぎない”と暮らしやすくなる
僕は会社員として働きながら、自分らしくシンプルに暮らしたいと考えています。
忙しい日々の中で、限られた時間と気力を「やるべき家事」に取られすぎないように、
できるだけ手間を減らす暮らしの仕組みを整えてきました。
この記事では、僕が実践している「家事をシンプルにする7つのルール」を紹介します。
1. 靴下は全て同じものにする
靴下をペアで探す時間、地味にストレスじゃないですか?
僕は全て同じ黒い靴下にしています。失くしても、片方が生き残るし、畳む必要もなし。
毎朝、考えずに済むことがひとつ減るだけで快適です。
2. 洗濯は“干さない”運用にする
ドラム式洗濯乾燥機は、正直一番導入してよかった家電。
洗濯物を干す→取り込む→畳む、という手間が全部なくなります。
しかも乾燥フィルターを毎回掃除するようにしたら、タオルもふわふわ。
3. 畳まない服の収納に切り替える
服は全てハンガーにかける or ボックス収納で“丸めて入れる”だけ。
「シワが気になる服」=「扱いにくい服」なので、そもそも買わない。
選びやすさ、戻しやすさが最優先です。
4. 掃除は“床に物を置かない”で8割解決
ロボット掃除機がしっかり掃除してくれるように、床に物を置かない暮らしを徹底。
サーキュレーターも浮かせ、ゴミ箱も壁掛け。
物理的に置けない部屋は、自然と散らからない。
5. 収納は“備え付けのみ”と決める
収納家具を増やすと、物も増える。
だから僕は「収納は引っ越し時の備え付けだけ」と決めている。
引き出し1段で下着・タオル・パジャマすべて収まるように、そもそも持ち物を減らす設計です。
6. 作り置きは“味付けなし”で応用する
週に1〜2回、鶏むね肉や温野菜、ゆで卵などを味付けなしで仕込んでおきます。
食べる直前に、ポン酢・カレー粉・塩レモンなどの調味料でバリエーションをつければ、飽きないし楽。
料理の「準備」はシンプルに、「食べる」は楽しく。
7. 家電やサービスは“判断基準”を明確にして導入
ロボット掃除機、ドラム式、ポット、炊飯器など、家電に任せること=自分の時間を守ること。
逆に、使わなくなるガジェットは買わない。
「自分が面倒だと思う動作を、1日1回以上やってるか?」で必要性を判断します。
おわりに:「頑張らない家事」が暮らしを整える
“ちゃんとやらなきゃ”と思うほど、家事は重たくなる。
でも、自分に合ったルールと仕組みでやれば、必要最低限で快適な暮らしは成立する。
家事は「気合」ではなく「構造」で回すもの。
家を快適にすることは、心の余裕をつくることにもつながる。

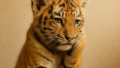
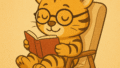
コメント